follow us

follow us
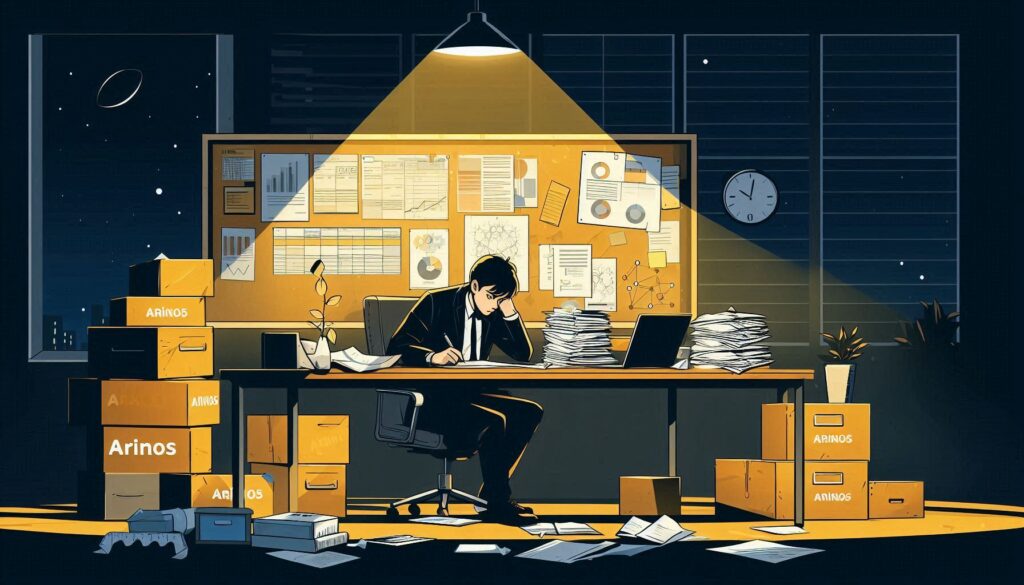
「P」というロボットをご存じでしょうか。2014年、大手通信事業者が「感情を持つ世界初のパーソナルロボット」として発表しました。発売初日に1,000台が一瞬で完売し、街の量販店や銀行の受付にも次々と立つようになりました。華やかな表舞台の裏側で、その「P」を支えるバックエンドの仕組みをつくることになったのが、当時まだ社員20名に満たなかった私たちArinosでした。
きっかけは、コンサルティング大手A社の先輩から教えて頂いた公募情報でした。「P」の問い合わせ対応から修理、代替機の手配、返送までを一気通貫で支える体制をゼロから構築してほしい──それが大手通信事業者のロボット事業会社からの要請でした。
正直に申し上げれば、私はそのとき「ロボット市場」に詳しかったわけではありません。しかし「誰もやったことのない領域でゼロから体制を作る」。その挑戦に惹かれ、即座に手を挙げました。
まず自ら一人で現場に入る
多くの応募があったことは間違いありませんが、私は市場価格を下回るコストで「自分自身を提供する」ことで、この案件への参加権を獲得しました。専門知識を持つ社員の方々の中に外部から入った唯一人でしたが、クライアントの社員以上に会議で発言し、意思決定を進めることが求められました。プレッシャーは大きかったです。
「P」は売れていましたが、アーリーステージのプロダクトゆえ、故障や不具合は頻発しました。関節や手足は壊れやすく、ネットワークや音声認識も安定しない。ユーザーからの問い合わせが殺到すればたちまち回らなくなる──これに備えた体制構築が私のミッションでした。
まず私は問い合わせ窓口の設計から入り、フローを一枚絵に描き出しました。「電話かフォームか」「一次切り分けは誰か」「代替機を出すのか」。現場を想像しながらタスクを一つずつ「TO DO」に落としました。ここで役立ったのは、かつて事務機プロジェクトで叩き込まれた「段取りの筋肉」でした。
未経験10人を一気に入れる
設計を固めたあと、短期間でスケールさせるために私は決断しました。未経験でも構わない、とにかく10人を一気に現場へ入れ、私が書いたTO DOを回す。若手人材向けサービスで起業志向の若者や第二新卒を集めました。
即戦力は望めません。そこで数名のマネージャークラスを外部から呼び、育成と品質担保を任せました。私は毎日フローを整備し、会議では敢えてジュニアに説明させ、場数を踏ませました。徹底したOJTで、早い者は数週間、遅くても2、3か月で戦力になりました。
仕事の量が質をつくる。この真理は10年前も、働き方が変わった今も同じです。結果が出ない時もあります。しかし「めちゃくちゃ頑張っているかどうか」。その姿勢こそが信頼を生み、成長につながるのです。
30人体制、クライアント社員を上回る
数か月後には体制は30人規模に。クライアント社員を上回る陣容となり、外部パートナーが現場の主戦力を担う異例の状況でした。会社としても大きな収益の柱に育ちました。
しかし数字以上に大きかったのは、人材と組織を一気にスケールさせる経験でした。事務機のプロジェクトでは「個」で戦う力を学び、カンボジアでは「現場に根づく力」を学びました。ここでは「人を束ね、仕組みで回す力」を学んだのです。
「常駐伴走支援」の意味
私たちのスタイルは「常駐伴走支援」でした。報告書を書いて終わりではなく、社員と同じ机で汗をかく。時に「社員以上だ」と言われるほど踏み込みました。その深さがあるから信頼を得られ、課題も見えてきます。
同時に、外部だからこそ言えることもありました。「ここはこう直した方がよい」としがらみなく伝えられるのは、信頼を得ているからこそ。両面あってこそ「伴走」の価値なのだと痛感しました。
最初の一人がすべてを決める
この案件で私は人材観を変えました。優秀な人を最初から揃えるには時間もコストもかかる。ならば、未経験者を現場に放り込み、育てながら成果を出す。外部経験者を少数入れて支え、全体を回す。そのためには、最初の一人が全貌を把握し、投入したリソースを即座に価値に変える設計を描いておくことが必須です。
ここでも「スーツケース一つで現場に飛び込める人材」というカンボジアの学びを生かしました。能力よりも、飛び込む胆力があるかどうか。組織はその「飛び込める人」で支えられるのだと実感しました。
いま振り返って思うこと
あのとき「一人では無理だ」と尻込みしていたら、この経験は得られませんでした。即戦力だけで固めようとしても30人のチームはできなかったでしょう。不安でも走り続け、仲間を信じて飛び込ませること。これこそが成果につながるのです。
「P」はやがてブームが去りましたが、この案件で得た「スケール伴走力」は今もArinosの血肉です。現場に深く入り、人と組織を一気に伸ばす。その経験があるからこそ、今「コンサルティングの民主化」を掲げ、資金・グロース・EXITの支援を担えるのです。
結び──「人と組織を伸ばす型」
事務機では段取りと忍耐、カンボジアでは現場と文化への根づき。そしてロボット事業では、人と組織をスケールさせる型を学びました。個からチームへ、チームから組織へ、未経験からプロへ──ビジネスを短期間でスケールさせる。その伴走のプロセスこそ、Arinosの真骨頂です。
初期のロボット市場は幻のように盛り上がり一旦落ち着きましたが、AIとの結合で新しい次元へ進もうとしています。人と組織を伸ばす型は消えません。あのとき「P」の現場で得た学びは、今も私の中で生き続けています。